
オフショア開発の契約形態にはいくつかの種類がありますが、その中でも近年注目されているのがラボ型開発です。特にDXやサービス開発をスピーディに進めたい企業にとって、専属チームを確保できるラボ型は有力な選択肢となります。本ページでは「ラボ型開発とは何か」を解説し、メリット・デメリットや他契約形態との違い、成功のポイントを整理した上で、どの国に委託するべきか比較検討できるようまとめます。
ラボ型開発とは、海外の開発会社に自社専属のチームを設け、中長期にわたって共同開発を行う契約モデルです。請負契約のように完成物を納品する形態ではなく、期間内でチームを稼働させ、必要に応じて機能追加や要件変更を柔軟に行えるのが特長です。自社の延長線上に開発部隊を構築するイメージに近く、開発体制の拡張や継続的な改善に適しています。
ラボ型開発の最大の魅力のひとつがコスト削減です。日本国内で同じスキルレベルのエンジニアを採用・維持するには非常に高い人件費がかかりますが、オフショア拠点であれば人月単価を半分以下に抑えつつ、同等以上のスキルを持つ人材を確保できます。
また、一度チームを立ち上げれば採用や教育コストが継続的に削減され、固定的な採用活動の負担から解放される点も大きな利点です。さらに、複数人を同時に稼働させることが可能なため、単発の外注に比べて効率的にプロジェクトを進められます。
プロジェクトのフェーズや市場状況に応じて、チームの規模を柔軟に調整できるのもラボ型開発のメリットです。新機能開発やリリース直前には一時的に人数を増やし、安定運用期には縮小するといった変動に対応しやすくなります。国内採用だと数ヶ月単位でしか人員を増やせないケースが多いのに対し、ラボ型は数週間単位でメンバーを増減できることも珍しくありません。
そうすることで、必要な時に必要なだけのリソースを確保し、コストを最適化できます。
請負型開発ではプロジェクトごとにチームが変わり、仕様や業務知識をその都度引き継ぐ必要があります。一方ラボ型開発では、同じ専属チームが長期間プロジェクトに携わるため、自社特有の業務フローや開発規約がチーム内に蓄積されます。結果として、次の案件や追加開発もスムーズに進み、無駄な説明や再教育の手間を削減できます。
このナレッジの積み重ねは長期的に大きなコスト削減につながると同時に、品質の安定化にも寄与します。
ラボ型開発はアジャイル開発やPoC(概念実証)に特に向いています。要件を固定してからスタートする請負型と異なり、契約期間内で自由にタスクを入れ替えたり追加できるため、市場の変化に即応できるスピード感があります。
スタートアップ企業や新規事業部門が、短期間で試作と改善を繰り返す際にも効果的です。結果として、リリースの早期化や競合に先んじた市場投入が可能となります。
ラボ型開発は単なる外注先ではなく、「自社の延長」として機能する仮想的な開発部門を持つイメージです。現地の採用・教育は委託先が担いつつ、自社は専属チームを長期的に活用できます。
社内の開発リソースを増やすのと同じ効果を得られるため、採用難に直面する日本企業にとって有力な解決策となります。
ラボ型は「専属チームを借りる」形態であるため、品質や進捗を委託先任せにはできません。自社側でのタスク管理やレビューが必要となり、一定のマネジメントリソースを割く必要があります。
メンバーのスキルが均一でない場合や、チーム内の入れ替えが多い場合には品質が安定しないリスクがあります。契約時点でメンバーのスキルセットを確認し、入れ替え基準を明確にしておくことが重要です。
ラボ型は中長期を前提とした契約形態であり、数ヶ月程度の短期プロジェクトにはコスト的に割高になるケースがあります。長期的に継続開発を行う体制を求める企業に適しています。
ラボ型開発を理解するには、他の契約形態と比較することが有効です。
それぞれに向き不向きがあるため、自社の案件規模や期間、開発スタイルに応じて選択することが重要です。
ラボ型開発は日本と海外の複数拠点で同時並行的に進むため、認識の齟齬が発生しやすいのが実情です。成功のためには、進捗報告のフォーマットや頻度をあらかじめ決めておくことが欠かせません。例えば週次ミーティングを固定化し、日次でタスク管理ツールを用いて状況を共有する仕組みを作ると、双方の不安を軽減できます。
また、重要な意思決定については必ず書面やチケットで残すことも有効です。
ラボ型契約では、開発メンバーのアサインは委託先に任されるケースが多く、スキルレベルにばらつきが出ることがあります。そのため、契約時にメンバーのスキルセットや経歴を事前に確認し、期待値に満たない場合は交代を依頼できる条件を盛り込んでおくべきです。
また、定期的にパフォーマンスを評価し、必要に応じて入れ替える基準を明文化することで、品質の安定化を図れます。
ラボ型は長期的な体制構築を目的とした契約モデルであるため、半年や1年といった中長期を前提に考えることが成功の鍵です。短期的に利用すると立ち上げコストの回収が難しく、コスト効率が悪化してしまいます。最低でも1年以上の活用を視野に入れることで、ナレッジの蓄積やチームの熟成が進み、本来のメリットを享受できます。
ラボ型開発は委託先に任せきりにするのではなく、日本側にも責任者やPMを配置して並走管理を行うことが不可欠です。進捗管理やレビュー、セキュリティ運用、欠陥対応の基準を日本側でコントロールすることで、品質を担保できます。特に「仕様変更の合意プロセス」や「バグ発生時の対応フロー」は、最初に契約書や業務プロセスで定めておくべきです。
海外拠点にデータを扱わせる以上、セキュリティ対策は欠かせません。アクセス権限の管理や監査ログの取得、個人情報の取り扱いに関するルールを明文化し、遵守させる体制を整えましょう。ISO/IEC27001などの国際認証を持つ企業を選ぶのも有効です。セキュリティを軽視した委託は長期的なリスク要因となるため、事前の確認を徹底することが成功の条件です。
ラボ型では稼働時間に対して費用が発生するため、「どれだけ成果が出ているか」を可視化する仕組みが必要です。タスク管理ツールやコードレビューシステムを活用して作業内容を透明化し、コストと成果のバランスを定期的に評価することで、投資対効果を最大化できます。
ラボ型開発は、オフショア開発を戦略的に活用したい企業にとって有効な選択肢ですが、委託する国によって効果は変わります。例えばコスト重視ならベトナム、コミュニケーション重視ならフィリピン、大規模案件ならインドといった選び方が可能です。自社の開発スタイルやプロジェクト規模に合わせて最適な国を選びましょう。
| 国名 | 平均開発単価* (USD/時) |
JSTとの時差 | 主なメリット | 主な注意点 |
|---|---|---|---|---|
| インド | 12 – 20 | −3 h30 m | 世界最大級のIT人材層、AI・クラウド等の先端技術に強い | 離職率・品質ばらつきが大きく、チーム管理が必須 |
| ベトナム | 14 – 19 | −2 h | コストと品質のバランスが高く、日系プロジェクト実績も豊富 | 人件費上昇・都市部集中による人材偏在 |
| フィリピン | 約 8 – 15 | −1 h | 公用語が英語、BPO業界で鍛えたコミュニケーション力 | 上級人材は単価が上振れ・通信インフラの地域差 |
| ウクライナ | 22 – 30 | −6 h(夏時間基準) | 欧州品質・数学/AI系スキルが高い | 戦時リスク・電力供給不安定 |
| タイ | 15 – 21 | −2 h | インフラ安定、日系企業が多く文化的親和性も高い | 英語対応は限定的でBrSEが必須、地方との単価差 |
| ミャンマー | 19 – 26 | −2 h30 m | ASEAN内で屈指の低コスト、若年層豊富 | 政治・通信の不安定さ、外貨送金規制 |
| バングラデシュ | 17 – 25 | −3 h | 若年人口比率が高く市場が急成長中 | 大規模案件経験者がまだ少なくプロセス成熟度が低い |
ラボ型開発とは、専属チームを海外に設けて中長期的に開発を進める契約モデルです。コスト削減やスピード感、ナレッジ蓄積など多くのメリットがある一方、マネジメントの負担や短期案件には不向きといったデメリットも存在します。請負契約・準委任契約との違いを理解し、自社にとって最適なモデルを選ぶことが重要です。
また、委託先としてどの国を選ぶかも成功の大きな要因です。インド、ベトナム、フィリピン、中国など、それぞれの国の特徴を比較しながら、自社に最もフィットする拠点を選定していきましょう。
漏えいは避けたい、古い基幹は止めたくない、戦略は現場まで落とし込みたい——オフショア開発の悩みは企業ごとに違います。
ここでは自社の目的に合う支援会社を選ぶことで、最短ルートで自社にあったパートナーに辿り着ける「目的別」インドのオフショア開発会社おすすめ3選」をご紹介します。
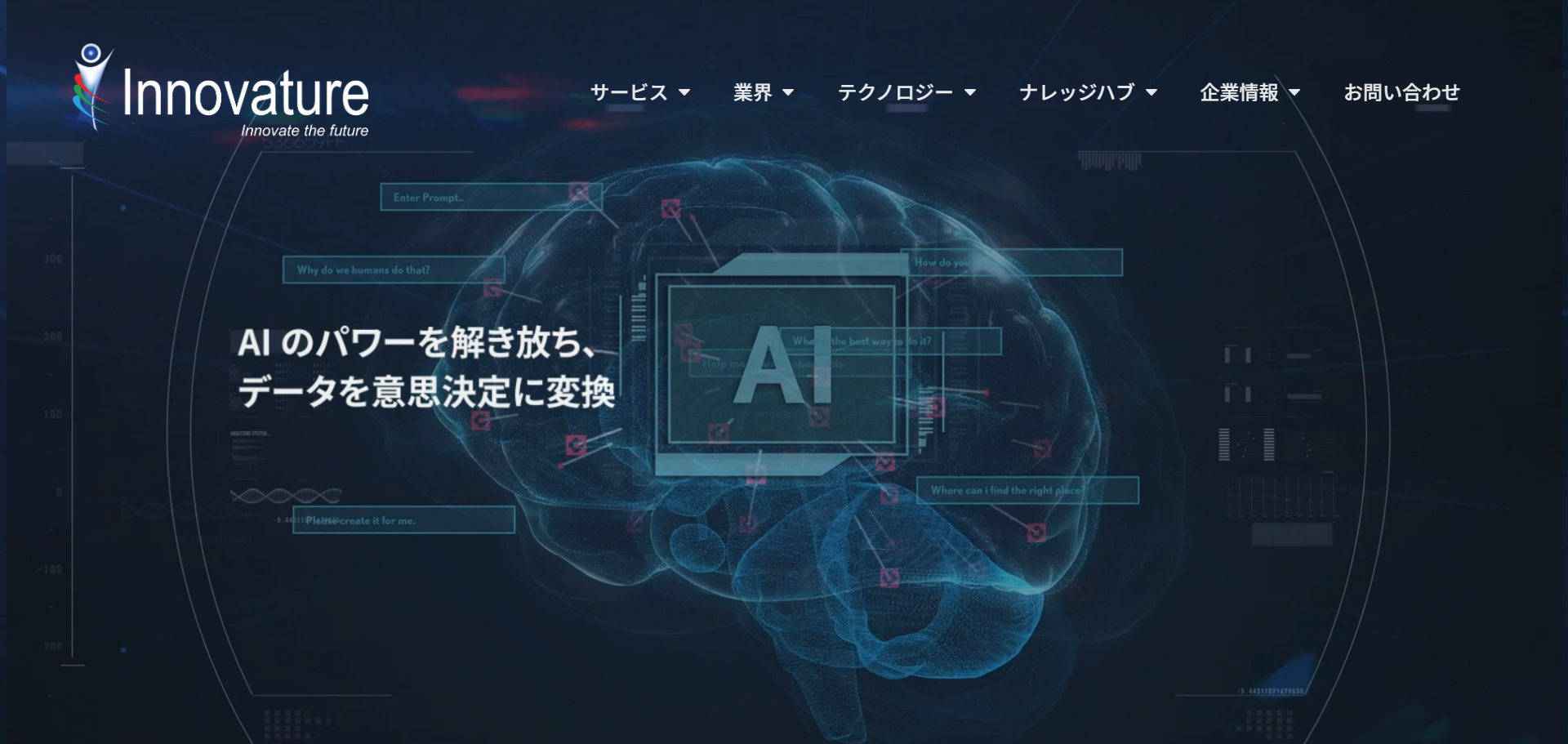
金融、電気通信、EC、広告&メディア、教育、ヘルスケアなど
KDDI、ドコモ、DNP、マクロミル、博報堂、ブリヂストン、リクルートなど

製造業、医薬品、小売業、メディア、電気通信など
※公式HPに記載なし

製造業、情報・技術、自動車、ハイテック、建設、教育、金融など
※公式HPに記載なし